特区申請紹介~福岡県の乗合タクシー事例
東京交通新聞に「タク・バス特区構想活性化」という見出しで全国の特区申請事例が紹介されていました。ここでは、その具体的な申請内容を紹介します。
まずは、福岡県(自治体)から出された「タクシー事業に係る増車後監査の要件緩和」という案件です。
現状の制度では、“特別監視地域においてタクシーの増車を行う場合には「増車7日前までの届出」と「増車後の監査」を受けなければならない”となっているところを、協議会で承認された場合のみ「増車後の監査」を外して欲しいというものです。
提案理由として、次のように書かれています。
“特別監視地域(特定特別監視地域を除く)において、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会、あるいは地域公共交通会議で了承された場合は、増車に伴う措置を「増車7日前までの届出」のみとし、監査の対象としない。現在、地域公共交通活性化・再生総合事業等において、乗合タクシーを実施する際に空き時間を利用して車両を活用する場合は、規制の対象となり、監査を受ける必要がある。
そのため、タクシー事業者としては空き時間にタクシーとして車両を有効活用する上で障壁となっている。一方で、上記協議会や地域公共交通会議には、交通事業者も構成員として入っており、加えて、国土交通省も連携計画の認定や地域公共交通会議の構成員として入っているため、供給過剰に繋がるような増車については未然に防止できる。
道路運送法第8条で規定されている「緊急調整地域」や供給拡大により運転手の労働条件の悪化を招く懸念が大きな「特定特別監視地域」と異なり、「特別監視地域」のみの指定の場合、過疎地域も含んでいる。このような地域においては、指定に至った理由は、車両数の増加ではなく、営業収益の減少によるところが大半と想定する。事業者にとっては、車両の空き時間の有効活用はコスト削減により、営業収益の増加に繋がるため、通達の趣旨にも沿ったものと考える。”
この背景としては、福岡県内のどこかで公共交通会議経由での乗合タクシーを計画したのだろうと思います。ところが、受ける側のタクシー会社に乗合タクシーに回す車両がなく、増車で対応したいが「増車後の監査」というリスクまで負えない、ということになったのでしょう。県の職員は、「そんなバカな規制なら特区でお願いしてみよう」という具合でしょう。
特措法って何なのか?全てを規制することにどれだけの意味があるのか?減車も大事ですが、活性化はもっと大事だろうと思うのです。パイが減っていくことを追い掛けていてもタクシーの市場は縮まるばかりなので、乗合分野など今後の発展が見込めるところは積極的に支援していくべきではないかと思います。
最後に、この件に関する国交省側の1次回答は「乗合タクシーで増車した車がどれだけ一般タクシーで使われるかわからないからNO」というものでした。
まずは、福岡県(自治体)から出された「タクシー事業に係る増車後監査の要件緩和」という案件です。
現状の制度では、“特別監視地域においてタクシーの増車を行う場合には「増車7日前までの届出」と「増車後の監査」を受けなければならない”となっているところを、協議会で承認された場合のみ「増車後の監査」を外して欲しいというものです。
提案理由として、次のように書かれています。
“特別監視地域(特定特別監視地域を除く)において、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会、あるいは地域公共交通会議で了承された場合は、増車に伴う措置を「増車7日前までの届出」のみとし、監査の対象としない。現在、地域公共交通活性化・再生総合事業等において、乗合タクシーを実施する際に空き時間を利用して車両を活用する場合は、規制の対象となり、監査を受ける必要がある。
そのため、タクシー事業者としては空き時間にタクシーとして車両を有効活用する上で障壁となっている。一方で、上記協議会や地域公共交通会議には、交通事業者も構成員として入っており、加えて、国土交通省も連携計画の認定や地域公共交通会議の構成員として入っているため、供給過剰に繋がるような増車については未然に防止できる。
道路運送法第8条で規定されている「緊急調整地域」や供給拡大により運転手の労働条件の悪化を招く懸念が大きな「特定特別監視地域」と異なり、「特別監視地域」のみの指定の場合、過疎地域も含んでいる。このような地域においては、指定に至った理由は、車両数の増加ではなく、営業収益の減少によるところが大半と想定する。事業者にとっては、車両の空き時間の有効活用はコスト削減により、営業収益の増加に繋がるため、通達の趣旨にも沿ったものと考える。”
この背景としては、福岡県内のどこかで公共交通会議経由での乗合タクシーを計画したのだろうと思います。ところが、受ける側のタクシー会社に乗合タクシーに回す車両がなく、増車で対応したいが「増車後の監査」というリスクまで負えない、ということになったのでしょう。県の職員は、「そんなバカな規制なら特区でお願いしてみよう」という具合でしょう。
特措法って何なのか?全てを規制することにどれだけの意味があるのか?減車も大事ですが、活性化はもっと大事だろうと思うのです。パイが減っていくことを追い掛けていてもタクシーの市場は縮まるばかりなので、乗合分野など今後の発展が見込めるところは積極的に支援していくべきではないかと思います。
最後に、この件に関する国交省側の1次回答は「乗合タクシーで増車した車がどれだけ一般タクシーで使われるかわからないからNO」というものでした。
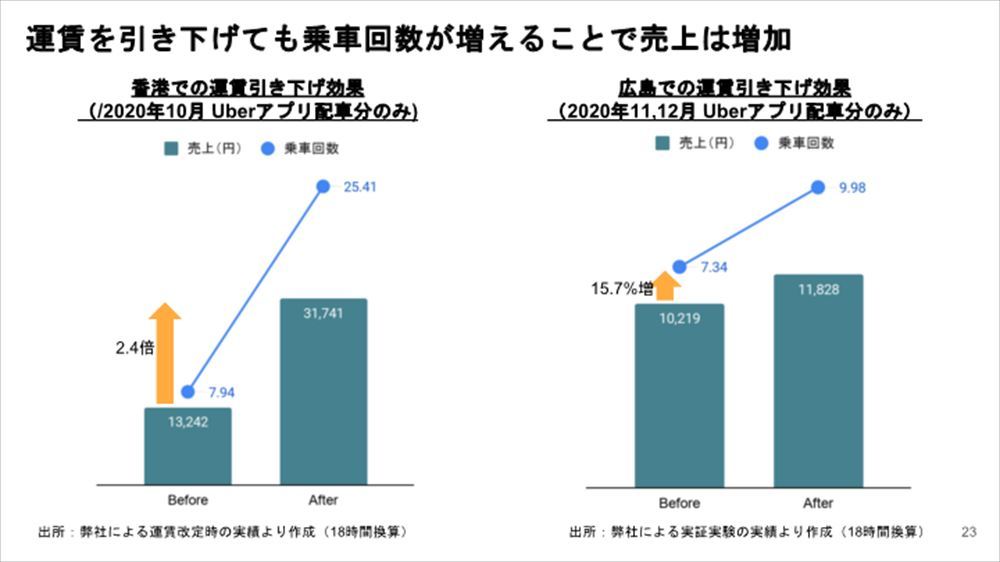

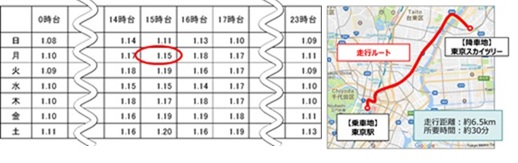
.png)
 (1).jpg)