福祉有償運送・対価の悩ましい問題
2日に「北九州市福祉有償運送運営協議会」が開かれ、委員として出席しました。
主な内容は、北九州市内9団体からの変更事項に関する協議と、下半期実績等の報告でした。
変更事項の協議の中で、「旅客から収受する対価の変更」については、とても判断が難しい問題であり、継続協議となりました。誰も反対もしていないのですが、即答で決議するには重い問題であったからです。
対価の変更というのは、運賃・料金のことで、ある1団体が
・初乗り3kmまで600円→2kmまで600に変更
(それ以降は1km毎に100円というのは変更なし)
という申請をあげてきました。
福祉有償運送における運賃の判断基準として、「タクシーの上限運賃の概ね2分の1以下」というものがあります。福祉有償運送を行なう団体としての選択は2つあり、ひとつが非営利として運営協議会に諮るもので、もうひとつが営利団体として当社のような営業許可を得るものです。営業許可を得るとしても、福祉輸送の場合は1台から可能であり、昔から比べるとかなり手続きが緩和されています。営業許可であれば運賃の制約はなく、タクシー上限までは上げることができます。要するに、団体としては手続き上あまり負荷の変わらない2つの選択があって、非営利を選択するからにはそれなりに運賃も安くなってしかるべきだということです。安いといってもどれくらいか判断に困るので、「概ね2分の1」となったのだと思います。
北九州のタクシー上限運賃が、初乗り1.6km650円ですから、1kmあたりで406円。上記申請で、1km当たりでは200円から300円への変更になり、タクシーの2分の1を大きく上回ってしまいます。
この団体は、当初3kmまで500円でしたが、運送単体での収支が賄えずに値上げをしてきています。それは事業の継続という意味では止むを得ないことだと思います。赤字だから止めるということよりも、値上げして維持しようという選択は理解できます。
ところが利用者側の視点で考えると、「頼りにしている外出のコストが上がっていく」という不満にならないだろうかと危惧されます。
これらのことを考えてみると、“福祉輸送全体の問題”が見えてきます。営利事業者も経営的に厳しい状態で従業員にも無理をさせている状態で、非営利の団体も厳しいということは、「移動のコストを誰が負担するのか?」という問題に突き当たります。個別輸送というものは、どうしてもコストがかかってしまう現実があるのに、利用する側はバス等の交通が利用できなくて交通費を負担するのが厳しい方です。このギャップはどこまでいっても埋まりません。
上記団体の申請に対しての話に戻りますが、一概に運賃が高いということでは判断ができず、「利用者にどんなサービスをしてどういったコストがかかっているか」を総合的に判断して、現実を直視した結論を出すことが大切だと思っています。
主な内容は、北九州市内9団体からの変更事項に関する協議と、下半期実績等の報告でした。
変更事項の協議の中で、「旅客から収受する対価の変更」については、とても判断が難しい問題であり、継続協議となりました。誰も反対もしていないのですが、即答で決議するには重い問題であったからです。
対価の変更というのは、運賃・料金のことで、ある1団体が
・初乗り3kmまで600円→2kmまで600に変更
(それ以降は1km毎に100円というのは変更なし)
という申請をあげてきました。
福祉有償運送における運賃の判断基準として、「タクシーの上限運賃の概ね2分の1以下」というものがあります。福祉有償運送を行なう団体としての選択は2つあり、ひとつが非営利として運営協議会に諮るもので、もうひとつが営利団体として当社のような営業許可を得るものです。営業許可を得るとしても、福祉輸送の場合は1台から可能であり、昔から比べるとかなり手続きが緩和されています。営業許可であれば運賃の制約はなく、タクシー上限までは上げることができます。要するに、団体としては手続き上あまり負荷の変わらない2つの選択があって、非営利を選択するからにはそれなりに運賃も安くなってしかるべきだということです。安いといってもどれくらいか判断に困るので、「概ね2分の1」となったのだと思います。
北九州のタクシー上限運賃が、初乗り1.6km650円ですから、1kmあたりで406円。上記申請で、1km当たりでは200円から300円への変更になり、タクシーの2分の1を大きく上回ってしまいます。
この団体は、当初3kmまで500円でしたが、運送単体での収支が賄えずに値上げをしてきています。それは事業の継続という意味では止むを得ないことだと思います。赤字だから止めるということよりも、値上げして維持しようという選択は理解できます。
ところが利用者側の視点で考えると、「頼りにしている外出のコストが上がっていく」という不満にならないだろうかと危惧されます。
これらのことを考えてみると、“福祉輸送全体の問題”が見えてきます。営利事業者も経営的に厳しい状態で従業員にも無理をさせている状態で、非営利の団体も厳しいということは、「移動のコストを誰が負担するのか?」という問題に突き当たります。個別輸送というものは、どうしてもコストがかかってしまう現実があるのに、利用する側はバス等の交通が利用できなくて交通費を負担するのが厳しい方です。このギャップはどこまでいっても埋まりません。
上記団体の申請に対しての話に戻りますが、一概に運賃が高いということでは判断ができず、「利用者にどんなサービスをしてどういったコストがかかっているか」を総合的に判断して、現実を直視した結論を出すことが大切だと思っています。
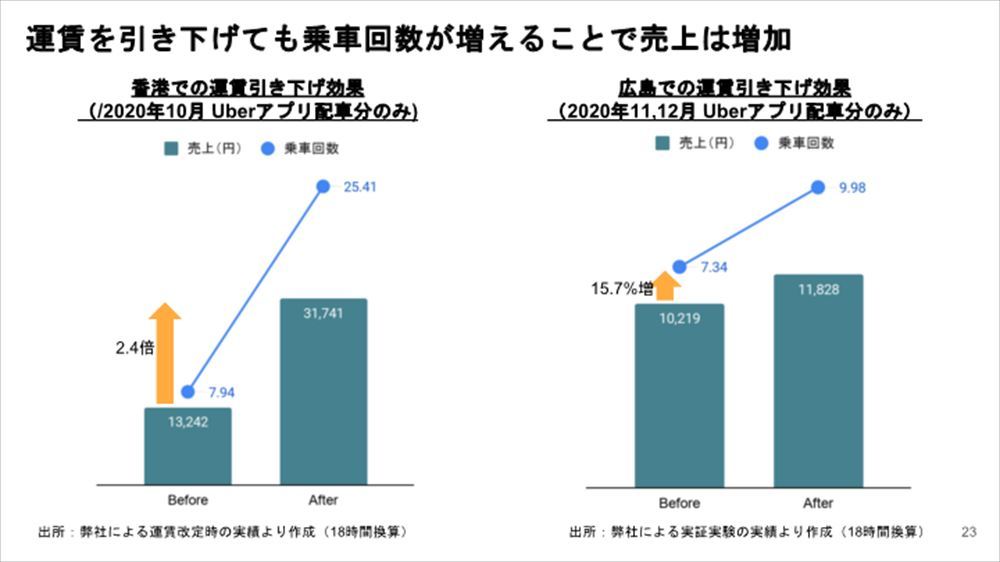

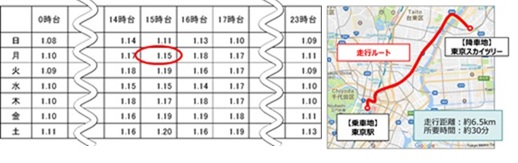
.png)
 (1).jpg)