適正車両数算定の解説
関東運輸局が示した適正車両数の算定方式が、業界紙等には掲載されていますが、後の会議等での話の中で、ほとんどの社長がこの式を理解していないことがわかります。協会の幹部の者まで理解していないので、スタート地点から話が噛み合わないのかと思うと、情けない限りです。本当は、最初にレクチャーでもしてあげたいところですが、出しゃばる訳にもいかず、いつもムヤムヤしてしまいます。
ついでですから、算定式を説明しておきます。
適正車両数=需要量÷(A/B)÷365÷実働率
ここで、需要量=2008年度の総実車キロ×対前年度比
A=過去5年間の平均総走行キロ×2001年度の実車率
B=過去5年間の平均延べ実働車両数
上記の式が書かれていますが、最初から考えようとしないと、意味もわからず過ぎてしまいます。
需要量とは、本来は今年度(2009年)の実車キロを出したいところですが、今年度の実績はまだ出ないので、昨年度の実績に前年度比を掛けることで、推定をしたものです。北九州全体であれば、北九州のタクシー全体の実車キロ(乗客の乗車キロ)を需要量としたものです。
この需要量に対して、何台のタクシーがあれば供給することができるかということで、1台のタクシーが1日80キロ実車するとしたら、それで割り戻したら必要な台数が出てきます。
上記、Bの実働車両数=実在車両数×365×実働率 なので、書き換えると、
適正車両数=2009年度の実車キロ/(5年間の平均走行キロ×2001年実車率)×実在車両数
5年間の走行キロの変化があまりないので、結局は2001年度の実車キロに対して、今年度がどれだけ減少したか、ということになります。
北九州では、2割程度減少していると思われるので、適正車両数は、現状の車両数×0.8程度になろうかと思います。
ただ、これが出たところで、「需要が減少した分だけ、どうやって車両を減らそうか?」という議論にしかなりません。「どうやって、以前の需要を取り戻そうか?」という議論にならないところが、これもタクシー業界の特徴なのでしょう。
ついでですから、算定式を説明しておきます。
適正車両数=需要量÷(A/B)÷365÷実働率
ここで、需要量=2008年度の総実車キロ×対前年度比
A=過去5年間の平均総走行キロ×2001年度の実車率
B=過去5年間の平均延べ実働車両数
上記の式が書かれていますが、最初から考えようとしないと、意味もわからず過ぎてしまいます。
需要量とは、本来は今年度(2009年)の実車キロを出したいところですが、今年度の実績はまだ出ないので、昨年度の実績に前年度比を掛けることで、推定をしたものです。北九州全体であれば、北九州のタクシー全体の実車キロ(乗客の乗車キロ)を需要量としたものです。
この需要量に対して、何台のタクシーがあれば供給することができるかということで、1台のタクシーが1日80キロ実車するとしたら、それで割り戻したら必要な台数が出てきます。
上記、Bの実働車両数=実在車両数×365×実働率 なので、書き換えると、
適正車両数=2009年度の実車キロ/(5年間の平均走行キロ×2001年実車率)×実在車両数
5年間の走行キロの変化があまりないので、結局は2001年度の実車キロに対して、今年度がどれだけ減少したか、ということになります。
北九州では、2割程度減少していると思われるので、適正車両数は、現状の車両数×0.8程度になろうかと思います。
ただ、これが出たところで、「需要が減少した分だけ、どうやって車両を減らそうか?」という議論にしかなりません。「どうやって、以前の需要を取り戻そうか?」という議論にならないところが、これもタクシー業界の特徴なのでしょう。
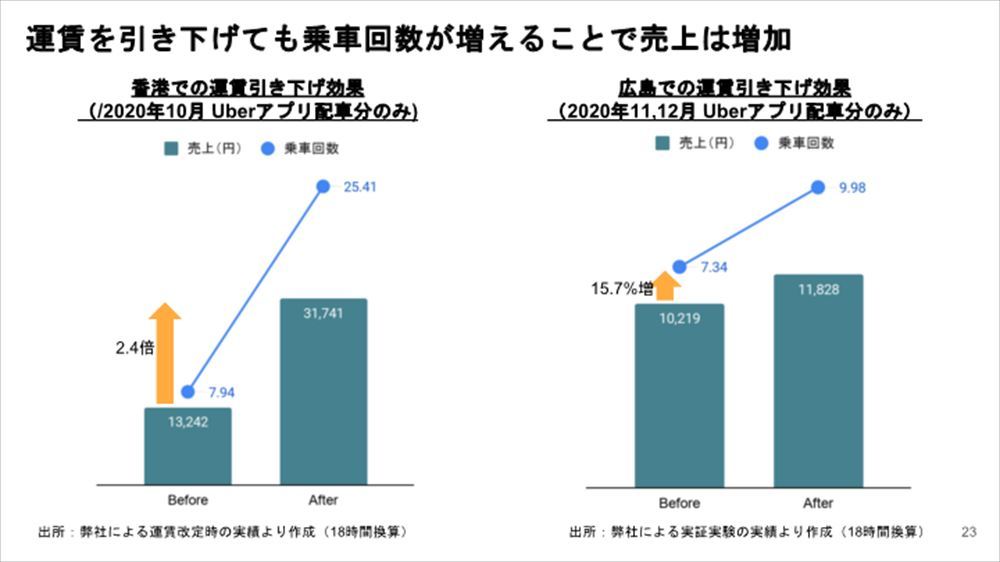
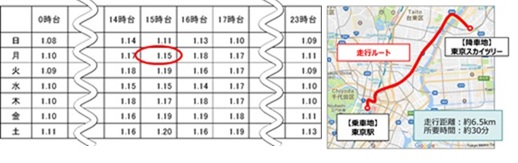
.png)
 (1).jpg)