業界誌掲載の“ラウンドテーブル”全文

9月7日付東京交通新聞掲載
運送業では、目的地に早く到着できるほど運賃が高くなるのが普通だ。学術的には、時間費用と運賃との合計が小さくなるように行動するので、移動の時間が短縮できることにコストをかける選択になる。流しのタクシーに乗車しようとする場合、待つ費用以上の価格差がない限り安いタクシーが選ばれることもない。移動という目的だけを考えた場合は、時間価値の重みは大きい。
ところが、タクシーだけは到着が遅くなるほど運賃が高くなる不思議な乗り物だ。時間距離併用運賃は、かつて諸先輩方が苦労して勝ち得た制度なのかもしれない。しかし、利用者の視点で考えた“運賃”とは思えない。素直に今の制度を肯定して考えてみると、タクシーは運送業ではなくサービス業を選択したものだとの結論になった。信号待ちでいくら、30分いくらという価格の設定は、運賃ではなくサービス料金の考え方だ。
タクシーの対価が、果たしてサービス料金でいいものかどうかということには異論がある。しかし、その方向転換には相当な困難を要するものと想像できるので、とりあえずはこの料金の考え方に合ったタクシーであるべきだと思う。すなわち、お客様が対価を支払ってもいいと思えるような環境や時間を提供することだ。1Q84のシンフォニエッタのような音楽や、他では得られないようなグルメ情報、車内でパソコンが開けるような工夫もいいかもしれない。「急がない場合でもタクシーを利用する」という選択者を増やしていく努力が必要だろう。
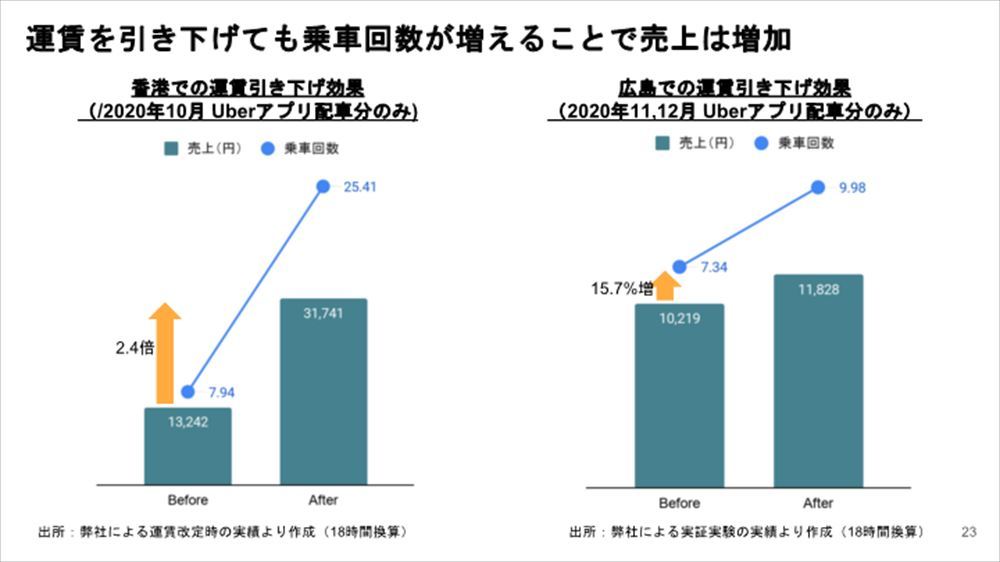
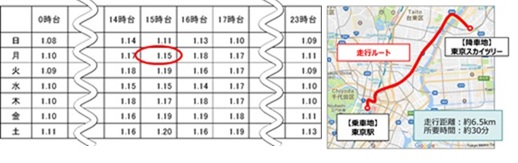
.png)
 (1).jpg)