「不当な競争を引き起こす場合」とは?
道路運送法第9条の三にタクシーの運賃認可に関することが定められています。その認可基準には、4つのことが書かれています。
1.適正な原価に利潤を加えたものを越えないこと。(上限制)
2.特定の旅客に対し不当な差別的取り扱いでないこと。
3.他のタクシーとの不当な競争を引き起こすものでないこと。
4.対距離制の場合、国土交通大臣がその距離を定めた時はこれによること。
安価な運賃が申請された場合には、3、の「不当な競争」になるかどうかが過去に争われてきました。こういう法律文は、定量的な基準が書かれていないので、結局は判例によることになります。
〈判例その1〉MK訴訟(昭和60年1月)
当時は、同一地域同一運賃という時代であったが、「適正原価、適正利潤の原則に合致し、不当な競争を引き起こすおそれがない場合は、異なる運賃を認可すべき。10分の1以下のシェアであること、流し、無線配車や貸切で営業している場合は、不当な競争を引き起こすことを否定」する判決で、国が負けました。
〈個人タクシー訴訟〉(平成21年9月)
ワンコインや最低運賃額は、車両数全体の1割にも満たない程度であり、不当な値下げ競争を引き起こすほどに多くの事業者がこれに追随するとも考えにくい。
――
両方の判決で共通しているのは、収支が合っていれば、1割に満たない会社が何をしてもいいという解釈です。この判例は、タクシーの特性を理解していない中で、素人並みの裁判官判断だと思います。法律を作った人の意図が十分に理解できているとは思えませんが、判例は判例であり、この判例を覆すような事実を作っていかねばなりません。
安価な運賃が認可された場合に、これに追随する動きをみせていかないと、この判例は覆ることがないでしょう。
1.適正な原価に利潤を加えたものを越えないこと。(上限制)
2.特定の旅客に対し不当な差別的取り扱いでないこと。
3.他のタクシーとの不当な競争を引き起こすものでないこと。
4.対距離制の場合、国土交通大臣がその距離を定めた時はこれによること。
安価な運賃が申請された場合には、3、の「不当な競争」になるかどうかが過去に争われてきました。こういう法律文は、定量的な基準が書かれていないので、結局は判例によることになります。
〈判例その1〉MK訴訟(昭和60年1月)
当時は、同一地域同一運賃という時代であったが、「適正原価、適正利潤の原則に合致し、不当な競争を引き起こすおそれがない場合は、異なる運賃を認可すべき。10分の1以下のシェアであること、流し、無線配車や貸切で営業している場合は、不当な競争を引き起こすことを否定」する判決で、国が負けました。
〈個人タクシー訴訟〉(平成21年9月)
ワンコインや最低運賃額は、車両数全体の1割にも満たない程度であり、不当な値下げ競争を引き起こすほどに多くの事業者がこれに追随するとも考えにくい。
――
両方の判決で共通しているのは、収支が合っていれば、1割に満たない会社が何をしてもいいという解釈です。この判例は、タクシーの特性を理解していない中で、素人並みの裁判官判断だと思います。法律を作った人の意図が十分に理解できているとは思えませんが、判例は判例であり、この判例を覆すような事実を作っていかねばなりません。
安価な運賃が認可された場合に、これに追随する動きをみせていかないと、この判例は覆ることがないでしょう。
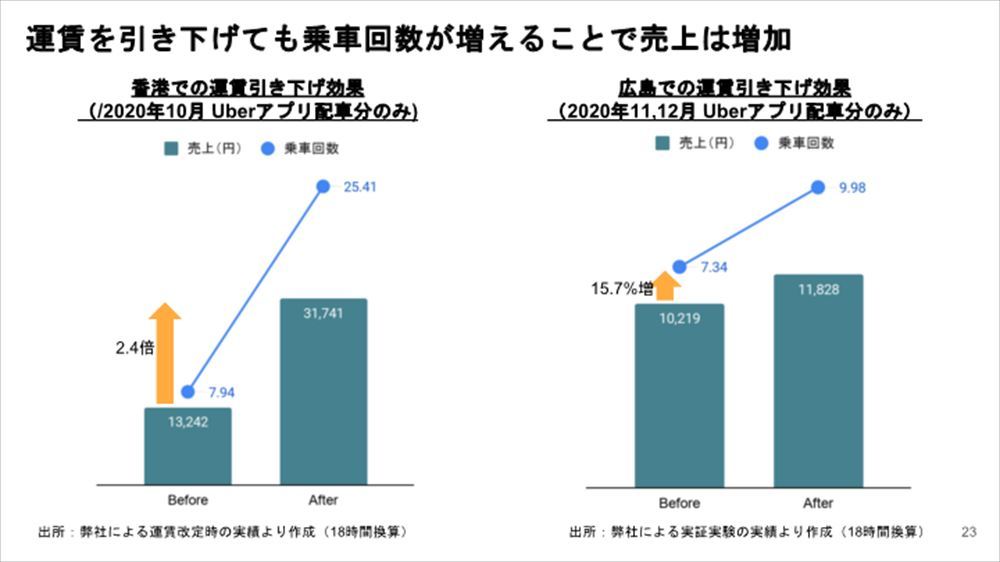

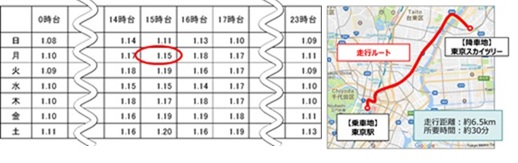
.png)
 (1).jpg)