タクシーの名義貸し
「タクシー事業における名義貸し行為の判断基準(案)」が国土交通省のパブリックコメントに出されている。
タクシーの法人事業者は、通常、乗務員を雇用し給与を支払っているが、雇用しているかに見えて実質上は個人事業主のような形態で契約している状態がグレーゾーンとして、従来から指摘がされていた。例えば、会社は乗務員に車両を貸与し、乗務員はその使用料として月額数十万円を会社に払い、売上は全て自分の収入となり、場合によっては保険料や修理代は自分持ち、という事例。あるいは、車両も乗務員が購入する事例もある。会社は、何のリスクも無しに車両台数分の収入が見込める利点があり、乗務員は売上を増やした分は自分の収入になる利点がある。タクシーは営業中は監視できないという事業の性格上、こういった委託形態が向いているという話もある。
今回示された判断基準は、
1.雇用関係
2.経理処理関係
3.運行管理関係
4.車両管理関係
5.事故処理関係
の5項目で、その事業形態が、タクシー事業の事業主体として負うべき危険や責務を他人に負わせ、実質的に他人が事業を営んでいることになっているか否かを判断するとしている。
この「名義貸し」として疑われている筆頭が京都のM○タクシー。もっと極端なのが大阪でのワンコイン系列の会社。この基準によると、M○タクシーは該当しないような気がしますが、地域のタクシー会社では結構該当する会社があるような気がします。
タクシーの法人事業者は、通常、乗務員を雇用し給与を支払っているが、雇用しているかに見えて実質上は個人事業主のような形態で契約している状態がグレーゾーンとして、従来から指摘がされていた。例えば、会社は乗務員に車両を貸与し、乗務員はその使用料として月額数十万円を会社に払い、売上は全て自分の収入となり、場合によっては保険料や修理代は自分持ち、という事例。あるいは、車両も乗務員が購入する事例もある。会社は、何のリスクも無しに車両台数分の収入が見込める利点があり、乗務員は売上を増やした分は自分の収入になる利点がある。タクシーは営業中は監視できないという事業の性格上、こういった委託形態が向いているという話もある。
今回示された判断基準は、
1.雇用関係
2.経理処理関係
3.運行管理関係
4.車両管理関係
5.事故処理関係
の5項目で、その事業形態が、タクシー事業の事業主体として負うべき危険や責務を他人に負わせ、実質的に他人が事業を営んでいることになっているか否かを判断するとしている。
この「名義貸し」として疑われている筆頭が京都のM○タクシー。もっと極端なのが大阪でのワンコイン系列の会社。この基準によると、M○タクシーは該当しないような気がしますが、地域のタクシー会社では結構該当する会社があるような気がします。
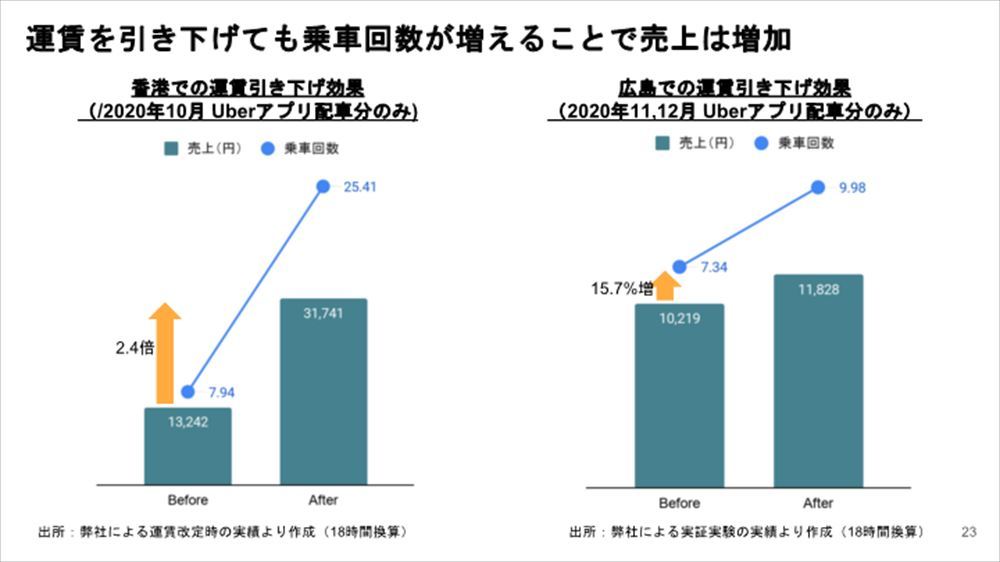

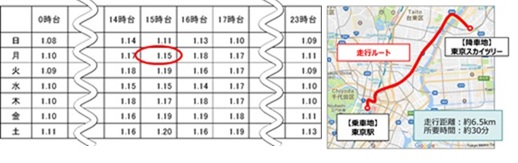
.png)
 (1).jpg)