自家用有償と規制改革
規制改革推進会議にて、「タクシー事業が成り立たない地域に限って自家用有償運送ができる」と国交省は答えています。現実を見てみましょう。自家用有償運送の3種類のうちの一つ、福祉有償運送はほとんどの地域でタクシーと共存しています。北九州市でも福祉有償運送の団体が9つあり、数百台の車両が稼働しています。本当にボランティアの団体もあれば、介護保険の指定を取って介護タクシーと同等のサービスを行っているNPOもあります。非営利団体と言っても、介護保険の収入は同じなので、会社と何が違うのだろうかと不思議に思います。
弊社のような介護タクシーの事業者は、「ぶらさがり」という制度で、自家用車での有償運送もできるので、弊社にも数台があり、二種免許を持たないヘルパーも通院乗降に携わっています。ただ、この「ぶらさがり」の許可では、ケアプランに基づくもの以外はできません。一方、同じ介護保険事業所でもNPO等での福祉有償運送許可であれば、そんな制約はありません。そんな不公平な競争下でも、同じ地域なのでサービスと技術の差で差別化を図っていくしかありません。
こんな現実があるのに、「タクシー事業が成り立たない地域しかNPO等の自家用有償はありません」と断言できるのは何故でしょうか?
タクシーには乗りたくても負担が高くて乗れないお客様が沢山います。お客様の中には、移動制約者の方も沢山います。ですから、タクシーが十分ある地域でも、市町村運営の自家用有償運送もあるし、福祉有償運送もあります。あるいは、タクシーでも行けるのに、乗合タクシーがあります。その理由は、タクシーでは満たされない客層があり、タクシーというよりはバスに代わる乗り物として、自家用有償が必要とされているのです。
国交省は、道路運送法の目的に沿って、市民のための交通を考えていく必要があるのではないでしょうか?
弊社のような介護タクシーの事業者は、「ぶらさがり」という制度で、自家用車での有償運送もできるので、弊社にも数台があり、二種免許を持たないヘルパーも通院乗降に携わっています。ただ、この「ぶらさがり」の許可では、ケアプランに基づくもの以外はできません。一方、同じ介護保険事業所でもNPO等での福祉有償運送許可であれば、そんな制約はありません。そんな不公平な競争下でも、同じ地域なのでサービスと技術の差で差別化を図っていくしかありません。
こんな現実があるのに、「タクシー事業が成り立たない地域しかNPO等の自家用有償はありません」と断言できるのは何故でしょうか?
タクシーには乗りたくても負担が高くて乗れないお客様が沢山います。お客様の中には、移動制約者の方も沢山います。ですから、タクシーが十分ある地域でも、市町村運営の自家用有償運送もあるし、福祉有償運送もあります。あるいは、タクシーでも行けるのに、乗合タクシーがあります。その理由は、タクシーでは満たされない客層があり、タクシーというよりはバスに代わる乗り物として、自家用有償が必要とされているのです。
国交省は、道路運送法の目的に沿って、市民のための交通を考えていく必要があるのではないでしょうか?
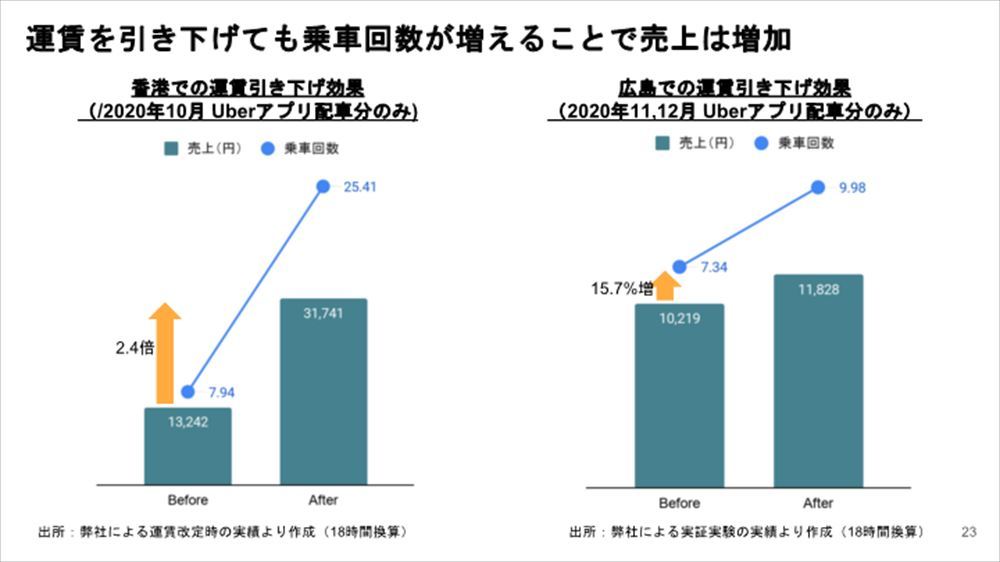

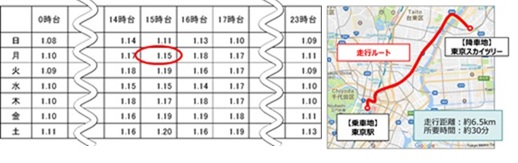
.png)
 (1).jpg)