日本では何故公共交通への公費投入に抵抗があるのか
「欧州では大気汚染や渋滞といった車の社会コストや高齢者ら車を運転できない人の移動の権利を考えて、公共投入への理解が定着している」と言われている(4月22日朝日新聞)。
欧州で路面電車の新たに導入ないし復活させた都市は80年以降、50を越えているという。その多くが、運賃収入と公費、半々で成り立っている。
仏東部のストラスブールは34年ぶりに路面電車を復活させ、利用を伸ばしていることで知られる。ダイヤは、都心で日中3分に1本。終点には駐車場が隣接している。市民の公共交通機関を使う回数は1人1日平均0.8回で、福岡市民の1.6倍。
北九州市が環境都市と言うが、基本的な政策が遅れていると思う。何回も言うが、北九州空港の390円/日という安価な駐車料金は、公共交通促進ということから完全に逆行している。市内のあちこちの道路拡幅工事やバイパス工事も、「そこまで必要だろうか?」と感じる所が多すぎる。
もっと、公共交通や徒歩や自転車で移動しやすい街、高齢者や障害者が安価に移動できる街にしていきたいのですが、何故日本人はそういった社会コストを負担しようとしないのでしょうか?
欧州で路面電車の新たに導入ないし復活させた都市は80年以降、50を越えているという。その多くが、運賃収入と公費、半々で成り立っている。
仏東部のストラスブールは34年ぶりに路面電車を復活させ、利用を伸ばしていることで知られる。ダイヤは、都心で日中3分に1本。終点には駐車場が隣接している。市民の公共交通機関を使う回数は1人1日平均0.8回で、福岡市民の1.6倍。
北九州市が環境都市と言うが、基本的な政策が遅れていると思う。何回も言うが、北九州空港の390円/日という安価な駐車料金は、公共交通促進ということから完全に逆行している。市内のあちこちの道路拡幅工事やバイパス工事も、「そこまで必要だろうか?」と感じる所が多すぎる。
もっと、公共交通や徒歩や自転車で移動しやすい街、高齢者や障害者が安価に移動できる街にしていきたいのですが、何故日本人はそういった社会コストを負担しようとしないのでしょうか?
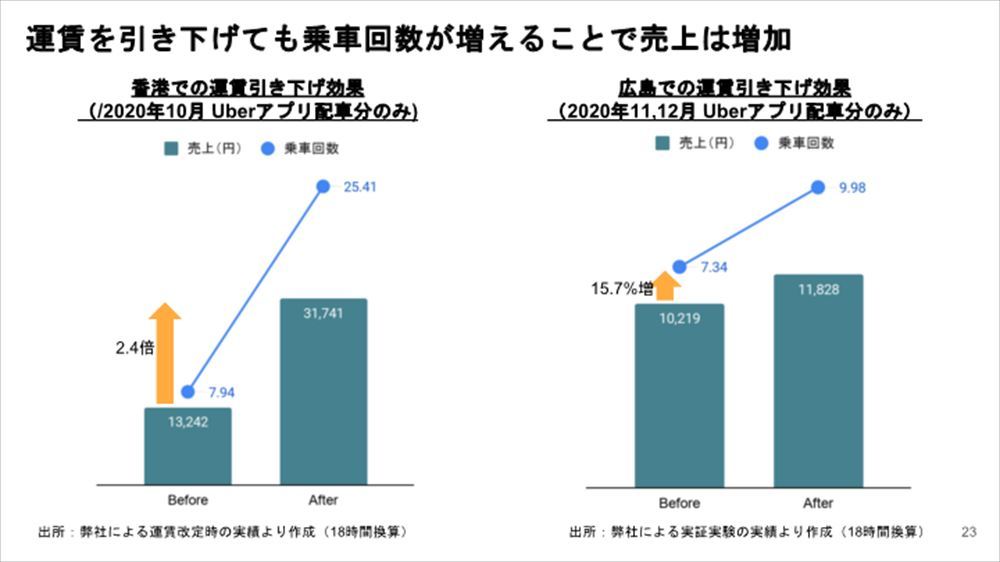

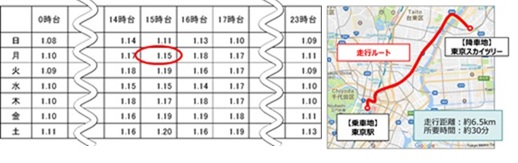
.png)
 (1).jpg)